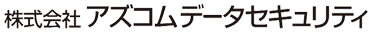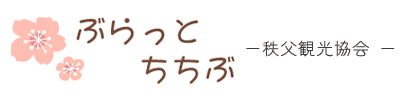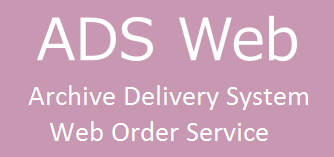【保管期間別】法令によって保管期間が決められている書類一覧
2025.09.30

企業が保有する書類は、種類ごとの保管期間が法令によって定められています。
そこで本記事では、書類保管に関する法令を遵守する必要性、そして書類の種類と関連する法令を保管期間別にご紹介します。
あわせて、保管期間が切れた書類の適切な処分方法もご紹介するので、法令を遵守しつつ、情報漏洩を防いで処分をしたいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
Contents
書類の保管期間を遵守すべき理由
法令によって定められた管理・保管をしなかった場合、法律違反となり罰則が課せられ、企業の社会的責任が失墜するリスクが高まります。
社会的責任が失墜することで取引先や株主といったステークホルダーからの信頼を失い、企業価値の低下を招く可能性もあります。
【保管期間別】書類の種類と関連する法令
保管が定められている書類の一例を、保管期間ごとにご紹介します。
なお、書類によっては複数の法令が該当し、保管期間が異なる場合もあるため、比較して長い方の法令を遵守するようにしてください。
永久保管が推奨されている書類一覧
以下の書類は法令による保管期間の定めは特にありませんが、書類の特性上、永久保存が推奨されています。
関連する法令:会社法
| 保管すべき書類 | |
| 法務・登記関連 | ・定款、定款変更履歴 ・登記事項証明書 ・法人の印鑑証明書 ・登記関連書類 |
| 株式・社債関連 | ・株主名簿 ・新株予約権原簿 ・社債原簿 ・株券喪失登録簿 |
| 訴訟・権利関係 | ・訴訟関連書類 ・知的財産の所有権に関する書類 |
| 官公庁・許認可関連 | ・官公庁提出書類 ・許認可、通達に関する重要書類 |
| 社内制度関連 | ・社内規定 ・社則 ・就業規則など |
| 契約・取引関連 | ・永続的な効力を持つ契約書類 |
| 製品・技術関連 | ・製品の開発・設計に関する書類 |
| 人事・労務関連 | ・重要な人事に関する書類 ・労働組合との協定書、団体交渉の記録 |
30年保管が定められている書類一覧
労働安全や健康管理に関する書類のなかでも、以下に挙げる特定の書類に関しては30年保管することが定められています。
| 関連する法令 | 保管すべき書類 |
| ・特定化学物質障害予防規則 | ・クロム酸等の空気中における濃度の定期測定記 ・特別管理物質についての作業の記録 ・特別管理物質を取り扱う業務に携わる労働者の特定化学物質健康診断個人票 |
| ・電離放射線障害防止規則※1 | ・放射線業務従事者の線量の測定結果記録 ・電離放射線健康診断個人票 |
※1:5年保存したあと、厚生労働大臣が指定する機関に該当する記録を引き渡すときはこの限りでないとされている
10年保管が定められている書類一覧
企業の意思決定の過程や財務状況など、主に総務や庶務に関連する書類は10年間の保管が義務付けられています。
| 関連する法令 | 保管すべき書類 |
| ・会社法 | ・株主総会議事録(本店備置き分) ・取締役会、監査役会議事録 ・各委員会議事録(指名委員会、監査委員会、報酬委員会) ・計算書類及び附属明細書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ・会計帳簿及び事業に関する重要書類(総勘定元帳、各種補助簿、株式申込書、株式割当簿、株式名義書換簿、配当簿、印鑑簿 など) |
| ・製造物責任法 | ・製品の製造、加工、出荷、販売に関する記録※2 |
| 特別な定めはないが保管が望ましいとされている書類 | ・満期、もしくは解約となった契約書 |
※2:民法では20年となっている
7年保管が定められている書類一覧
以下のような税金に関する書類、労働安全衛生に関する書類などは7年の保管を義務付けられているものが多いです。
| 関連する法令 | 保管すべき書類 |
| ・法人税法 | ・取引に関する帳簿(仕訳帳、現金出納帳、固定資産税台帳、売掛帳、買掛帳 など) ・決算に関して作成された書類(取引に関する帳簿以外の書類) ・現金の収受、払出し、預貯金の預入、引出しの際に作成された取引証憑書類(領収書、預金通帳、借用書、小切手、手形控、振込通知書 など) ・有価証券の取引に関する証憑書類(有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書 など) ・取引証憑書類(請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票 など) |
| ・電子帳簿保存法 | ・電子取引の取引情報に係る電磁的記録(注文書、契約書、送り状、領収書、見積書 など) |
| ・所得税法 ・租税特別措置法施行規則 | ・給与所得者の扶養控除等申告書 など |
| 租税特別措置法施行規則 | ・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 |
| ・消費税法 ・消費税法施行令 ・消費税法施行規則 | ・課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書、インボイス など※3 ・資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿 |
| ・国税通則法 | ・源泉徴収簿 (賃金台帳) |
| ・粉じん障害防止規則 | ・粉じん濃度の測定記録、測定結果の評価記録 |
| ・じん肺法 | ・じん肺健康診断記録 ・じん肺健康診断に係るエックス線写真 |
※3:5年経過後、帳簿または請求書等の保存が必要
5年保管が定められている書類一覧
5年の保管が定められている書類は、総務や人事、労働安全などさまざまなものが該当します。
| 関連する法令 | 保管すべき書類 |
| ・会社法 | ・事業報告、監査報告、会計監査報告 (本店備置き分) ・会計参与が備え置くべき計算書類、附属明細書、会計参与報告 |
| ・金融取引法 | ・有価証券届出書、有価証券報告書及びその添付書類、訂正届出書(報告)の写し |
| ・所得税法施行令 ・所得税法施行規則 ・租税特別措置法施行令 ・租税特別措置法施行規則 | ・金融機関が保存する非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄異動申告書、非課税貯蓄勤務先異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書 などの写し ・金融機関等が保存する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書 などの写し ・金融機関等が保存する退職等に関する通知書 |
| ・労働基準法施行規則 | ・企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項の記録 ・労使委員会議事録 |
| ・家内労働法施行規則 | ・家内労働に関する帳簿 |
| ・労働安全衛生規則 | ・一般健康診断個人票 |
| ・身元保証二関スル法律 | ・従業員の身元保証書 |
| ー | ・誓約書などの種類・契約期限を伴う覚書、念書、協定書 など ・重要な内容の発信、受信文書 |
| ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 | ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し ・産業廃棄物処理の委託契約書 |
| ・有機溶剤中毒予防規則 | ・有機溶剤等健康診断個人票 |
| ・鉛中毒予防規則 | ・鉛健康診断個人票 |
| ・四アルキル鉛中毒予防規則 | ・四アルキル鉛健康診断個人票 |
| ・特定化学物質障害予防規則 | ・特定化学物質健康診断個人票※4 |
| ・高気圧作業安全衛生規則 | ・高気圧業務健康診断個人票 ・高圧室内業務の減圧状況の記録 |
| ・電離放射線障害防止規則 | ・線量当量率または線量当量の測定の記録 ・放射性物質の濃度測定の記録 ・放射線事故に関する測定の記録 |
※4:クロム酸等は30年の保管が必要
3年保管が定められている書類一覧
3年保管が定められている書類には以下のようなものが該当します。
| 関連する法令 | |
| ・労働基準法※5 ・労働基準法施行規則 | ・労働者名簿・賃金台帳※6 ・雇入れ、解雇、退職に関する書類 ・災害補償に関する書類・賃金のその他労働関係の重要書類(労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書 など) |
| ・労働者災害補償保険法施行規則 | ・労災保険に関する書類 |
| ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 | ・労働保険の徴収、納付等の関係書類 |
| ・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | ・派遣元管理台帳 ・派遣先管理台帳 |
| ・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 | ・身体障害者であることを明らかにすることができる書類(診断書等) |
| ・労働安全衛生規則 | ・安全委員会議事録 ・衛生委員会議事録 ・安全衛生委員会議事録 ・救護に関する訓練の記録 ・安全衛生のための特別教育の記録 |
※5:改正労働基準法の施行日以後に期間が3年から5年に延長されたが、経過措置として当面は3年が適用される
※6:国税通則法では、7年間の保管が義務付けられている。
1〜2年保管が定められている書類一覧
以下に該当する書類の保管期間は、1年もしくは2年の保管が定められています。
| 関連する法令 | 保管すべき書類 |
| ・金融商品取引法 | ・臨時報告書、自己株券買付状況報告書及びそれぞれの訂正報告書の写し |
| ・雇用保険法施行規則 | ・雇用保険に関する書類※7(雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届け など) |
| ・健康保険法施行規則 ・厚生年金保険法施行規則 | ・健康保険、厚生年金に関する書類 (被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書、標準報酬改定通知書 など) |
※7:労働保険の保険料の徴収等に関する法律、または同施行規則では3年保管
保管期間が一年未満の書類
以下のように株主総会に関する書類は、株主総会の開催日から起算して3ヶ月保管することが義務付けられています。
| 関連する法令 | 保管すべき書類 |
| ・会社法 | 株主総会の代理権を証明した文書・株主総会の議決権行使に関わる文書 |
保管期間が定められた書類を保管する方法
保管期間が定められている書類は、紛失したり誤って処分したりしないよう、厳格な保管・管理が求められます。
紙媒体で保管
紙媒体での保管は一番オーソドックスな方法ですが、その都度書類が増えてしまい、管理も煩雑になりやすいです。
そのため、欲しい書類がすぐに見つからない、紛失してしまう、保管スペースが圧迫されるといったデメリットがあります。
電子化して保存
書類作成時のデータのまま保管する、使用した書類をスキャンしてデータ化するといった保管方法は、年度や種類ごとの分類がしやすいです。
しかし、スキャンの必要がある書類が多い場合は時間と手間がかかるといったデメリットがあります。
外部へ委託する
書類管理の専門業者なら、紙媒体のまま、またはデータ化したうえで保管するなど、ニーズに合わせた対応をしてもらうことが可能です。
また書類保管専門業者として高いセキュリティ体制を構築しているケースが多く、情報漏洩リスクも低減できるといったメリットもあります。
保管期間が切れた書類の処分方法
保管期間が切れた書類をいつまでも処分しないままでいても法的な罰則が課せられる可能性があります。
保管期間が切れてた書類の処分方法をご紹介します。
シュレッダー処分
シュレッダーを使用した処分は、オフィス内で手軽に行うことができますが、書類の量によっては多くの手間と時間を必要とします。
また、裁断の細かさによっては復元されて情報漏洩につながるリスクも伴います。
焼却処分
焼却すれば確実に書類を処分することができますが、CO2排出やダイオキシンの発生など、環境への配慮が必要です。
溶解処分
書類を完全に溶かして再生紙として生まれ変わらせる溶解処分は、書類の復元ができないだけでなく持続可能な資源の創出方法として近年注目を集めている処分方法です。
保管期間の定められた書類の管理はアズコムデータセキュリティまで
アズコムデータセキュリティでは、紙媒体の保管はもちろん、データ化したうえでの保管・管理にも対応しております。
データ化した書類は、弊社独自のADSWebシステムにより確認や変更を手軽に行っていただくことが可能です。
また、不要となった書類の溶解処分にも対応しているため、保管〜処分までの一連の業務についてワンストップ対応を実現しております。
溶解処分後は溶解証明書の発行をしておりますので、安心して監査に望んでいただくことも可能です。
法律に則った書類保管をしたうえで、情報漏洩リスクを抑えた処分まで一貫して委託したいとお考えの方は、まずはお気軽にアズコムデータセキュリティまでお問い合わせください。
料金表
| 料金項目 | 仕様 | 参考料金(税別) |
|---|---|---|
| 保管料 | 規格サイズ:W430×D335×H320 | 御見積/ケース |
| 入出庫料 | 対象:文書保存箱 | ¥80/ケース |
| 集配料 | 適用区域:東京都23区 | ¥1,000/ケース |
| 廃棄料 | ・処理方法:溶解処理 ・証明書発行料を含みます |
¥450/ケース |
| 文書保存箱 販売料 | 10枚1セットでの販売となります | ¥350/ケース |
まとめ
企業が保有する書類にはさまざまなものがあり、関連する法律によって保管期間が定められています。
しかし、自社で保管・管理・処分を行う場合は多くの手間と時間がかかるだけでなく、紛失や情報漏洩といったリスクを伴います。
法律を遵守したうえで、安全に書類の保管や処分を行いたいとお考えの方は、ぜひアズコムデータセキュリティまでご相談ください。
お預かりした書類やデータを安全に保管・管理させていただくだけでなく、適切な処分まで一貫して対応させていただきます。