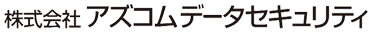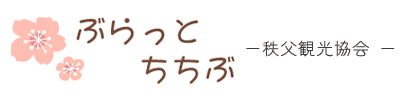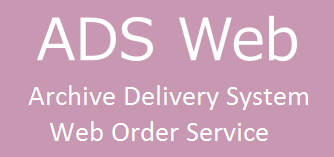書類の保管期間を遵守しよう!破った場合のペナルティ・影響は?
2025.05.21

企業にはさまざまな重要書類があり、なかには法律によって一定期間の保管が義務付けられているものもあります。
しかし、ルールを把握しないまま誤って書類を廃棄してしまうと罰則が科され、企業としての信頼性を失い経営に大きな影響を与えるおそれもあります。
本記事では、代表的な書類の保管期間を紹介するとともに、万が一違反した場合にどのようなペナルティがあるのかを詳しく解説します。
Contents
書類の保管期間が定められている理由

契約書や帳簿といった重要な書類は一定期間の保管期間が定められています。
保管期間が定めらている背景は次のとおりです。
法的義務遵守のため
企業や個人事業主は、所得税法や会社法などに基づき帳簿や契約書類・取引記録などを一定期間保管することが求められています。
たとえば、法人税法では帳簿書類の保存期間を定めており、これに違反すると青色申告の取り消しや過料といった罰則の対象となることも。
法令違反による罰則を回避し、法的なトラブルを未然に防ぐためにも、企業は一定期間にわたって書類を保管しておかなければなりません。
税務調査や監査へ対応するため
税務調査や監査が行われた際に、過去の書類が必要となるケースは少なくありません。
たとえば、申告内容に疑義が生じたときは、過去の帳簿や請求書を提示することで正当性を証明できる可能性があります。
また、社外監査においても同様に、適正な会計処理や業務運営を裏付ける証拠として書類の提示が求められることがあります。
そのため、決算が終わったからといって書類を破棄するのではなく、一定期間は保管しておく必要があります。
証拠保全のため
取引先や顧客との契約に何らかのトラブルが生じた際、訴訟に発展するケースもありますが、この際に書類が重要な証拠となります。
契約違反や債権回収の問題が生じた場合、それを裏付ける証拠がなければ自社の主張が通りにくく、法的に不利になる可能性があります。
一定期間にわたって書類を適切に保存しておくことは、自社の権利を守るための有効な防衛策になります。
企業の信頼性担保のため
企業において何らかの不祥事が発覚したり、疑いが生じたりした場合、株主や取引先、監督官庁などに対して正確な情報を提示しなければなりません。
しかし、書類が適切に保管されていないと、過去にどのような取引があったのかや、どういったプロセスで業務が行われてきたのかを証明することができません。
企業としての信頼性を回復するためにも、一定期間は書類を保管しておき、過去の業務履歴をいつでも確認できる体制を整えることが重要です。
コンプライアンス強化のため
企業の社会的責任や法令順守への関心が高まる中、書類の適切な保管はコンプライアンス強化の一環として不可欠です。
一定期間にわたって書類を保管することで、不正や情報の隠ぺい防止につながるほか、社員に対しても法令順守の意識を根付かせる機会となり、組織全体のガバナンス向上につなげることができます。
【種類別】書類の保管期間

一口に書類といってもさまざまなものがあり、根拠となる法律や保管期間も異なります。
以下にあげる代表的な書類と保管期間について解説します。
法的・税務関連の書類
法人の決算書や帳簿類は、法人税法においても会社法においても一定期間の保管が義務付けられています。
そのため、取引先や顧客との契約上のトラブルに備え、10年間は保管しておくようにしましょう。
【対象書類例】
- 会社の決算書・帳簿
- 領収書・請求書
- 雇用関係書類(雇用契約書・労働者名簿・賃金台帳など)
- 契約書
業務・取引に関する書類
取引に関する書類は主に会社法に関連するものが多く、保存する事が定められています。
また、納品書などの書類および記録は消費税の算出根拠ともなるため、一定期間保存しておく必要があります。
【対象書類例】
- 取引先との契約書
- 取引記録・納品書
- 社内規定・議事録
個人情報・顧客情報に関する書類
顧客リストには個人情報が含まれるため、個人情報保護法に基づいた取り扱い、そして利用目的が達成された際は速やかに廃棄しなければなりません。
また、カルテは医師法に基づき、診療が終了した日から一定期間保管しておかなければならず、これは閉院した場合も同様です。
【対象書類例】
- 顧客リスト
- カルテ
書類の保管期間を遵守しない場合のペナルティ・影響
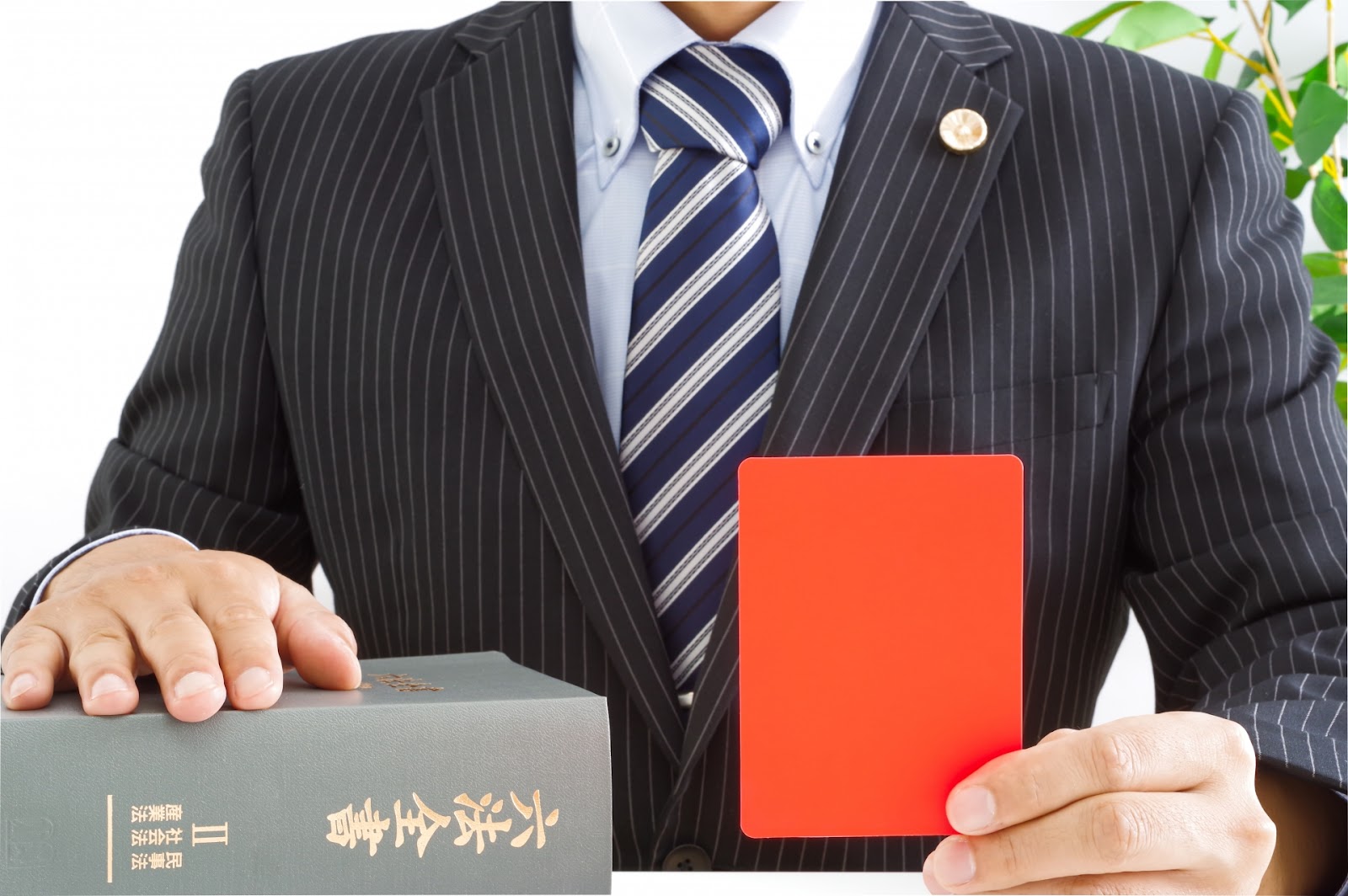
さまざまな法律によって書類の保管期間が定められていますが、これに違反した場合どのようなペナルティが課されるのでしょうか。
経営に与える影響も含めて詳しく解説します。
税務罰則
税務懲罰とはその名の通り、法人税法や所得税法・消費税法といった税法上のペナルティを指します。
具体的には、過少申告加算税や重加算税・青色申告の取り消しなどが挙げられます。
また、加算税の対象とはならなくても、税務調査において「推計課税※1」が適用される可能性があります。
本来納付すべき金額よりも多額の税金を支払うことになり、経済的ダメージは極めて大きくなります。
※1:実際の取引内容にかかわらず税務署が独自に課税額を決定する課税
労働基準法違反
雇用契約書や労働者名簿、賃金台帳などの保管義務を怠ると、労働基準法第に基づき罰金が科される可能性があります。
個人情報保護法違反
個人情報は利用目的に応じて厳密に管理しなければなりません。
個人情報保護法違反とみなされた場合、個人情報保護委員会からの勧告や命令が下されたり、罰金が科される可能性があります。
裁判・紛争などで不利になる可能性
たとえば従業員との間で労働契約に関するトラブルが発生した場合、書類を適切に保管できていないと企業側が労働時間や支払い実績を証明できず、従業員の主張がそのまま通ってしまうケースもあります。
その結果、書類不足が原因で多額の賠償金が請求されてしまうおそれもがあります。
企業の信頼低下
法令違反によるペナルティが軽微であったとしても、企業にとっては法令違反という事実そのものが信頼低下を招くこともあります。
コンプライアンス意識の低さが企業価値やブランド価値を損なう結果にもつながるため、日ごろから適切な書類管理が重要です。
書類を安全かつ適切に管理するためには
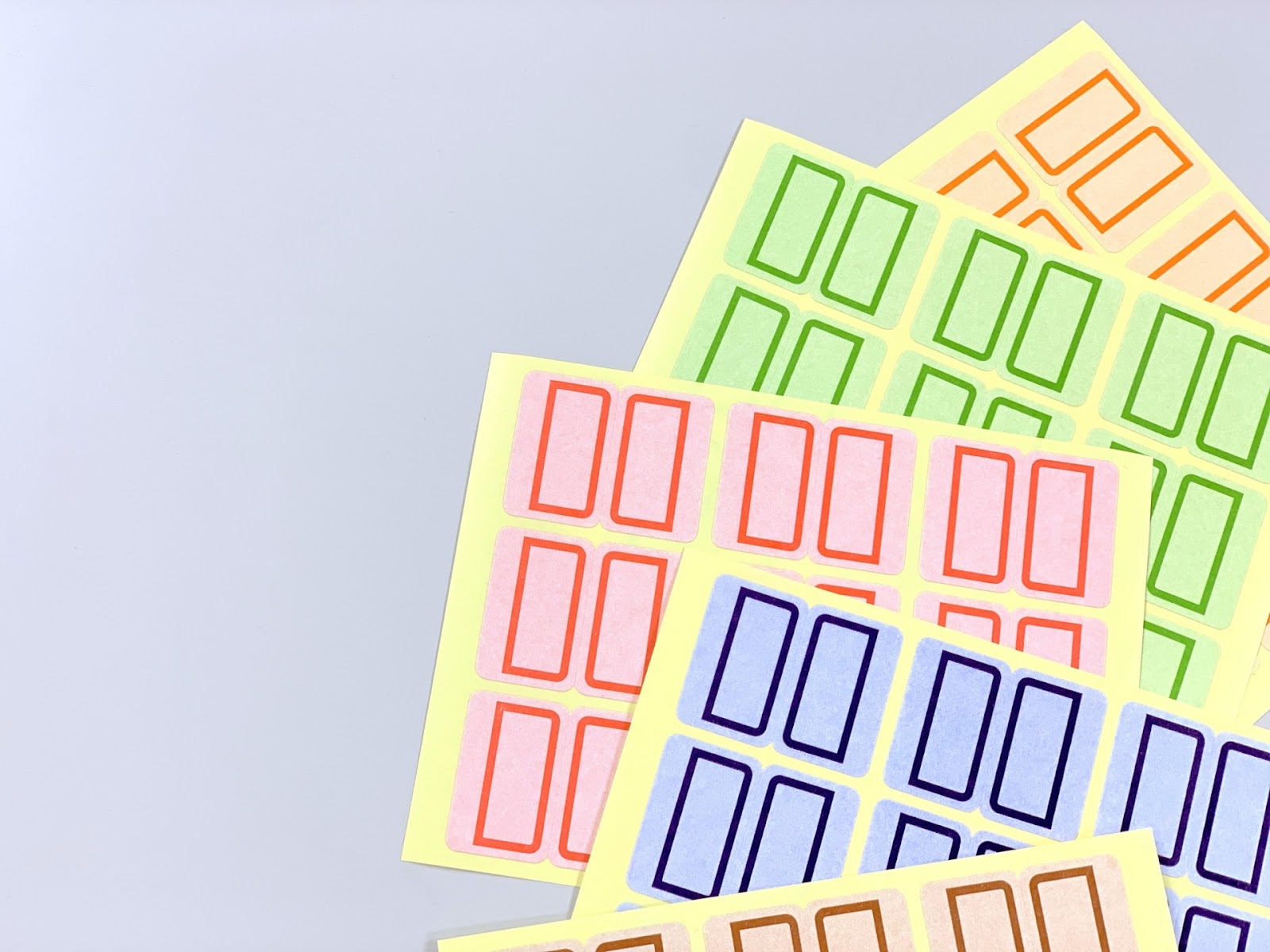
書類の数が増えるほど保管や管理に手間がかかったり、どこに保管したか分からなくなるケースは少なくありません。
そこで、安全かつ効率的に書類を管理するための方法やコツをご紹介します。
分類とラベル分け
一口に書類といってもさまざまなものがあるため、まずは種類ごとに分類し、わかりやすくラベリングすることが大切です。
たとえば「契約書」や「会計書類」、「人事関連」などのカテゴリを設け、保管日や廃棄予定日も記載しておくことで管理がしやすくなります。
書類によってはどの分類に属するのか判断が難しい場合もあるため、ルールを社内で統一し全社員に共有しておくと管理しやすくなります。
閲覧権限の厳格化
閲覧や編集・移動などの操作に対して、担当者に応じて権限を設定しておくことも大切です。
特に個人情報や契約書などは、限られた人のみがアクセスできるようにしたり、電子管理の場合はID・パスワードによる認証やログ管理を導入したりすることも効果的です。
保管期間が過ぎた書類の定期的な廃棄
オカン起源のすぎた書類をいつまでも保管しておくと、書類によっては法令違反に該当する場合があります。
特に、個人情報を含む書類に関しては、用途終了後に迅速な廃棄をすることが求められています。
保管期間をすぎた書類はしっかりと処分を行い、処分した日時を控えておくと監査などでも提示できるのでおすすめです。
書類保管サービスへの外注
社内の書類保管スペースや管理体制に限界がある場合、専門業者による書類保管サービスを活用することもおすすめの方法です。
書類保管サービスは、万全のセキュリティ設備が整った場所で書類を安全に保管できるだけでなく、検索システムによる書類の閲覧や取り寄せ、保管期間が過ぎた書類の廃棄対応まで委託できるため、業務負担の軽減にもつながります。
書類の適切な保管ならアズコムデータセキュリティまで!

書類保管サービスはさまざまな事業者が提供しており、月々のコストもまちまちです。
しかし、コストの安さだけで選んでしまうとセキュリティ体制に不備があったり、災害から大切な書類を守れなかったりといった不安も残ります。
アズコムデータセキュリティの保管サービスは、書類やCD/DVD、X線フィルムなどさまざまな媒体に対応しており、専用のWebシステムにより保管物の確認や閲覧も可能です。
また、保管倉庫は地盤が強固な埼玉県秩父市にあるため、万全のセキュリティ環境のもと安全に保管することができます。
さらに、保管期間が過ぎて不要になった書類は、お客様の同意のもとでデータ抹消処理施設において無開梱のまま溶解処理を行なっているため、廃棄時の情報漏洩リスクも抑えることが可能です。
信頼性が高い書類保管サービスをお探しの企業様は、ぜひ一度アズコムデータセキュリティへご相談ください。
料金表
| 料金項目 | 仕様 | 参考料金(税別) |
|---|---|---|
| 保管料 | 規格サイズ:W430×D335×H320 | 御見積/ケース |
| 入出庫料 | 対象:文書保存箱 | ¥80/ケース |
| 集配料 | 適用区域:東京都23区 | ¥1,000/ケース |
| 廃棄料 | ・処理方法:溶解処理 ・証明書発行料を含みます |
¥450/ケース |
| 文書保存箱 販売料 | 10枚1セットでの販売となります | ¥350/ケース |
まとめ
契約書や請求書、顧客リストなどの重要書類は法律によって保管期間が定められており、これに違反した場合さまざまなペナルティが科されます。
また、法令違反という事実そのものが企業の信頼性を低下させ、取引先や顧客との関係性に悪影響を与えてしまうこともあるでしょう。
書類の保管に関する法令は多岐にわたり複雑ですが、「知らなかった」では済まされないため、今回ご紹介した内容を理解し適切な管理を心がけましょう。
もし、自社内に保管スペースが確保できなかったり、管理に多くの手間がかかる場合は、ぜひアズコムデータセキュリティの保管サービスをご検討ください。