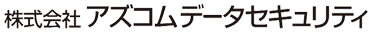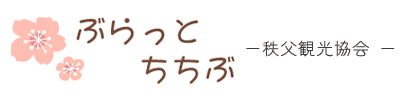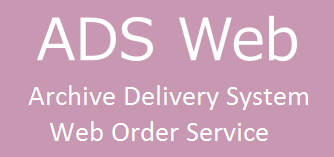法定保存文書の保存期間は?管理方法・処分の注意点も詳しく解説
2025.08.23

企業が取り扱う文書のなかには、法的に保存期間が定められているものが多く、適切な保管・管理が必要です。
そのため、法律に則った保管・管理を行うだけでなく、保管期限の切れた文書は速やかに処分をしなくては、コンプライアンス違反になる可能性があります。
そこで本記事では、法的に保存期間が定められている「法定保存文書」の定義や関連する法律を詳しく解説します。
あわせて、代表的な文書の保存期間の一例、管理のポイントもご紹介するので、「自社の文書を適切に保管・管理がしたい」とお悩みの方はぜひ参考にしてください。
Contents
法定保存文書の定義と適用される法律
はじめに、「法定保存文書」の定義、そして関連する代表的な法律を解説します。
法定保存文書とは?
法定保存文書とは、法律によって保存が定められている文書全般を指し、企業の取り扱う文書の多くが該当します。
定められている保存期間内で処分してしまうと、監査時に不利益が生じたり、コンプライアンス違反として罰則が課せられたりするケースもあるため、文書ごとに整理を行い、適切な管理をすることが求められます。
法定保存文書が関連する代表的な法律
法定保存文書に関連する代表的な法律には、次のようなものが挙げられます。
- 会社法
- 商業登記法
- 国税関係法令(法人税法・消費税法・所得税法など)
- 電子帳簿保存法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 建設業法・建築士法(建設業者や設計事務所向け)
上記のほか、個人情報保護法によって個人情報が記載された文書の取り扱いも定められており、「利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない(第二十二条)」と定められています。
法定保存文書の保存期間例
法定保存文書に関連する法律ごとの保存期間、そして関連する文書の一例をご紹介します。
| 法律 | 保存期間 | 関連する文書例 |
| 会社法 | 原則10年間 | ・株主総会議事録・取締役会議事録・計算文書(貸借対照表・損益計算書など)・事業報告書・定款や株主名簿、株券喪失登録簿 など |
| 商業登記法 | 10年間(登記に関連するもの) | ・登記事項証明書写し・商業登記申請に用いた文書控え など |
| 国税関係法令 | 7年間(青色申告の場合) | ・領収書や請求書、仕訳帳、総勘定元帳・棚卸表や決算関係書類、帳簿類・電子取引のデータ(電子帳簿保存法の対応が必要) |
| 電子帳簿保存法※1 | 原則7年間(税務署が定める) | ・電子帳簿・電子スキャン文書・電子取引データ |
| 労働基準法 | 3年間(2020年の改正により5年への延長もあり) | ・労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・労働条件通知書や就業規則、36協定届 など |
| 労働安全衛生法 | 原則5年間(一部は30年) | ・健康診断結果や面接指導記録・産業医指導記録、安全衛生委員会議事録 など |
| 建設業法・建築士法 | 5年間以上 | ・工事請負契約書・施工体制台帳・監理報告書 など |
※1:一定の条件下でPDF等の電子データ保存が可能
(注:上記表内の保存期間は2025年8月調べ)
法定保存文書を管理するポイント
法定保存文書を煩雑に取り扱った場合、定められた期限前に破棄してしまったり、保管期限の切れたあとも保存をしてしまうなど、さまざまなリスクを伴います。
法定保存文書を適切に管理するためのポイントをご紹介します。
適切な管理体制の構築
法律に則った文書管理をするためには、まず管理体制をしっかり構築することが大切です。
管理責任者の配置や文書の取り扱いルールの設定などを行うこととあわせて、社内全体への周知も徹底しましょう。
セキュリティの強化
例えば、紙媒体の文書であれば鍵付きキャビネットに保管したうえで管理責任者が鍵を管理、取り扱い記録簿を用意するなど、セキュリティ体制を強化しましょう。
また、電子媒体の保管についてはセキュリティソフトを強化する、パスワードを定期的に変更するなども必要です。
定期的なチェック
法定保存文書は、ただ管理体制やセキュリティ体制を強化すればよいだけではありません。
文書をリスト化し、文書が全て揃っているか定期的なチェックを行い、保管期限の切れているものがあれば迅速に処分するようにしましょう。
保存期間が切れた文書の安全な処分方法
保存期間が切れた文書の処分は、次のような方法で処分されることが多いです。
裁断処分
裁断処分は、シュレッダーなどを使って裁断する方法で、オフィス内でも手軽に行うことができます。
しかし、裁断の細かさによっては復元されてしまい、情報漏洩のリスクが伴います。
焼却処分
焼却処分は、文書を完全に処分することができますが、安全性や煙などへの配慮が必要です。
また、焼却時の温室効果ガスの排出やダイオキシンの発生、焼却に伴う灰の処分方法など、環境問題を引き起こすといったデメリットが多いです。
溶解処分
溶解処分は、近年高まっている環境問題へ対応した処分方法です。
処分すべき文書を完全に溶解したうえでリサイクル紙に生まれ変わるため、持続可能な資源の創出方法として注目されています。
法定保存文書の管理・処分ならアズコムデータセキュリティにお任せください!
アズコムデータセキュリティでは、高いセキュリティによる環境での適切な文書管理をご提供しています。
また、弊社独自のADSWebシステムにより、お客様がスムーズに文書の確認・取り出しをしていただくことも可能です。
お預かりしている文書が切れた場合も、お客様の同意のもとで提携するデータ抹消処理施設による溶解処分にも対応しております。
厳重なセキュリティ体制のもとで文書保管を行い、適切な処分もまとめて依頼したいとお悩みの方は、ぜひアズコムデータセキュリティまでご連絡ください。
料金表
| 料金項目 | 仕様 | 参考料金(税別) |
|---|---|---|
| 保管料 | 規格サイズ:W430×D335×H320 | 御見積/ケース |
| 入出庫料 | 対象:文書保存箱 | ¥80/ケース |
| 集配料 | 適用区域:東京都23区 | ¥1,000/ケース |
| 廃棄料 | ・処理方法:溶解処理 ・証明書発行料を含みます |
¥450/ケース |
| 文書保存箱 販売料 | 10枚1セットでの販売となります | ¥350/ケース |
まとめ
企業が取り扱う文書の多くは法的な保存期間が定められているだけでなく、期限の切れた文書は速やかに処分することも求められています。
しかし、文書管理を適切に行うためには管理責任者の配置やセキュリティ体制の強化など、時間とコストを要します。
「法律に則った文書管理がしたいけど管理が大変」「管理するためのリソースが足りない」とお困りの方は、まずはお気軽にアズコムデータセキュリティまでご相談ください。
厳重な管理体制と独自のシステムにより、お客様からお預かりした大切な文書を適切に保管・管理をさせていただきます。