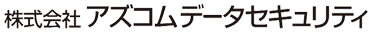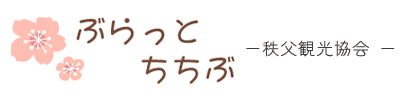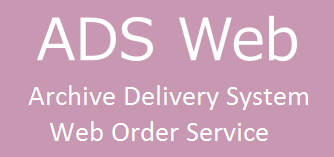機密文書などの個人情報を含む書類の正しい廃棄や処分方法とは?
2025.07.28

契約書や申込書・請求書など、日常の業務や生活の中で個人情報を含む書類を扱う機会は少なくありません。
個人情報の漏洩は思わぬトラブルや法的リスクを招くおそれがあるため、適切な方法で処分することが求められます。
本記事では家庭でできる基本的な対策から企業に求められるルールまで、個人情報を含む書類を安全に処分するための方法を解説します。
法律上の留意点にも触れながら、実践しやすい内容を確認してください。
Contents
個人情報を含む書類の処分が重要な理由
個人情報が大切だとは分かっていても、どうしてそこまで処分を重視しなければならないのか、明確な理由を知らないまま対応している方も少なくありません。
決められた工程に沿って正しく処分しなければならない理由として、次のような点が挙げられます。
- 情報漏洩により第三者に悪用されるリスクがある
- 個人情報保護法などの法令違反につながる
- 顧客や取引先の信頼を損なう可能性がある
- 損害賠償や訴訟などの経済的リスクを負う場合がある
- 企業・組織のブランドイメージが著しく低下する
- 社内外での管理体制の甘さを疑問視される
情報漏洩により第三者に悪用されるリスクがある
個人情報が記載された書類を適切に処分しなかった場合、第三者による不正利用につながる可能性があります。
住所や電話番号・銀行口座情報などが悪用され、なりすましや詐欺被害に発展する可能性もゼロではありません。
個人情報保護法などの法令違反につながる
個人情報保護法では、不要となった個人情報の適切な消去が求められ、不適切な処分によって法令違反と認められた場合は行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
顧客や取引先の信頼を損なう可能性がある
情報漏洩は、単に法律上の問題というわけではありません。
顧客や取引先からの信頼を失うことは、ビジネスへ長期にわたって影響を及ぼす可能性もあり、対応が遅くなるほど信頼の回復が難しくなります。
損害賠償や訴訟などの経済的リスクを負う場合がある
漏洩した情報の内容によっては、被害者から損害賠償請求がされる可能性があります。
また、話し合いによる解決ができなかった場合は訴訟に発展する可能性もあり、経済的リスクは大きくなるでしょう。
企業・組織のブランドイメージが著しく低下する
個人情報の漏洩は企業の管理責任を問われるため、企業ブランドのイメージ低下につながる恐れがあります。
そのため、顧客離れや取引先との関係悪化に拍車がかかる可能性があります。
社内外での管理体制の甘さを疑問視される
外部からだけでなく、社内の従業員からも「情報管理に対する意識が低い」とみなされる可能性があります。
こうした印象は離職率の上昇や採用活動への影響にも波及しかねません。
処分対象となる個人情報書類の具体例
一口に「個人情報を含む書類」といっても、その範囲は多岐にわたります。
思わぬものに個人情報が含まれているケースがあるため、適切な判断が重要です。
名簿・申込書・アンケートなど
学校や地域活動・イベント運営などで使用される名簿や参加申込書には、複数の個人情報が記載されていることが一般的です。
これらの書類は不用意に廃棄せず、慎重な扱いが求められます。
契約書・請求書・領収書に個人情報が含まれる場合
取引先との契約書や請求書・領収書にも、氏名・住所・銀行口座情報などが記載されていることがあります。
個人や法人を問わず、取り扱いには十分に注意することが大切です。
書類以外に注意すべき媒体とは
紙の書類だけでなく、USBメモリやCD・DVDなどの記録メディア、コピー用紙の裏紙や付箋などにも個人情報が記載されている場合があります。
こうした小さな部分にも目を向け、あらゆる媒体を処分対象として把握しておくことが大切です。
個人情報保護法に基づく処分のルール
個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護法」をはじめとする関連法令に基づき、適切な対応が求められます。
特に、廃棄する場合は次のような具体的なルールが明文化されているため、内容をしっかり理解することが大切です。
利用目的の特定と目的外利用の禁止
個人情報は、収集時に明示した利用目的に沿って使用することが原則として決められています。
不要になった場合には、当初の目的以外で使用することなく、目的を失った情報として適切に削除することが重要です。
個人データの消去義務
保有する必要がなくなった個人情報については、安全かつ確実に消去しなければなりません。
廃棄の方法が不適切であったり、目的もなく保有を続けていたりする場合、情報漏洩と判断されるリスクがあります。
第三者提供の制限
本人の同意を得ることなく、第三者へ個人情報を提供することは禁止されています。
廃棄するとなった場合も、その過程で他者に情報を閲覧される恐れがある場合、情報漏洩に該当する可能性があります。
個人情報保護委員会による処分と罰則
情報漏洩が発覚した際は、個人情報保護委員会による調査や行政指導が行われます。
重大な違反だと認められた場合、勧告や命令といった強い指示のほか、罰金刑が科されることも珍しくありません。
データの安全管理措置
廃棄までの期間も含め、日頃から個人情報を安全に管理するための措置が必要です。
技術的な部分だけでなく、物理的な対応の両面にわたって、管理体制を整備する必要があります。
本人による請求権
本人によって個人情報の開示・削除を求める権利も保証されています。
正当な請求があった場合に即対応できるよう、日頃からの備えとして情報の保管・廃棄履歴を細かく管理することが大切です。
参考:政府広報オンライン|「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルール
参考:e-GOV 法令検索|行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
安全な処分方法の種類と選び方
個人情報を含む書類は、情報漏洩を防ぐ為にも安全に処分することが必須です。
次に挙げる処分方法の概要と選び方を解説します。
シュレッダー
もっとも一般的な手段として挙げられるのが、シュレッダーを使用した裁断処理です。
クロスカットやマイクロカットなど裁断の方法によってセキュリティレベルが異なるため、個人情報を含む書類の場合はより細かく裁断できるタイプが適しています。
手軽に導入できる点が魅力である一方、大量の書類を処理する際は不向きな面もあります。
焼却処分
自治体の焼却施設を利用し、書類を燃やしてしまうという方法もあります。
灰にしてしまうことで復元のリスクがなくなり、情報漏洩のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
ただし燃焼に関する安全管理や排気対策が必要となるため、一般家庭で大量の書類を処分するのは現実的ではありません。
溶解処理
製紙会社などの専門業者が提供している「溶解処理サービス」を利用するという手もあります。
書類を溶液に溶かして細かくし、再び紙としてリサイクルする仕組みであり、復元はほぼ不可能です。
SDGsの観点からも良い取り組みだとされており、近年さらに注目を集めています。
自治体の個人情報書類処分サービス
一部の自治体では、住民向けに個人情報書類の専用回収サービスを実施しています。
指定日に回収された書類は、専門処理施設で安全に処分されます。
地域によっては利用条件が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
自宅でできる? 個人情報書類の処分方法
個人でも十分な対策を講じることで、個人情報漏洩のリスクを抑えられます。
自宅でできる個人情報書類の処分方法をご紹介します。
シュレッダーで裁断細断し燃えるゴミとして出す
自宅用の小型シュレッダーを使用し、個人情報部分を確実に裁断することで、漏洩のリスクを避けられます。
裁断後は「燃えるゴミ」として出すのが一般的であり、一般的な家庭ゴミ同様手軽に処分できるでしょう。
ゴミ処理施設へ持ち込む
大量に書類を処分したい場合は、地域が運営しているゴミ処理施設へ直接持ち込むといった選択肢もあります。
各家庭に配布されるゴミ収集スケジュールや自治体のホームページを確認し、分別ルールや受け入れ可能な書類の範囲・持ち込み可能な日時などを確認しておくと安心です。
書類溶解サービス(専門業者による溶解処理)を利用する
書類溶解サービスは、事業者だけでなく個人でも利用が可能です。
専門の業者が運営しているため、手軽さはもちろんのこと安全性の観点からも安心して利用できるでしょう。
直接持ち込むには距離がある場合も、宅配便などで書類を送付し、業者がまとめて処理してくれる場合もあります。
書類溶解サービスでは、処理後に証明書の発行も受けられます。
証明書があることにより、個人情報を正しく処分したことが認められ、企業や個人を守ることにつながります。
企業・団体における書類処分の適切な手順
企業や団体においては、組織的かつ法令に準拠した書類の処分が求められます。
処分方法を誤ると重大な法的責任や信用問題につながるため、「単なる書類だから」と軽視せず、慎重な対応が必要です。
書類処分の基本手順と社内ルール整備の重要性
第一に、社内における書類管理のルールを策定することは必要不可欠です。
分類・保存期間・処分基準などを明確にしたうえで、社員への周知と定期的な見直しが求められます。
部署や文書の種類によって処分フローを区別すれば、工程の手間や無駄・ミスを最小限に抑えられるでしょう。
機密文書と一般書類の処分方法の違いと選び方
機密文書には個人情報や業務上の重要情報が含まれるため、より厳重な処分方法を選ぶ必要があります。
これらは焼却処分や溶解処理が一般的であり、内部で処理しきれない場合は、専門業者への委託が望ましいです。
重要な情報を含まない一般的な書類については、社内のシュレッダーにて処理することが許容される場合もあります。
安全・確実な書類廃棄のための業者選定と証明書発行の流れ
業者に処分を委託する際は、適切な処理能力と信頼性を確認することが大切です。
処理後に「溶解証明書」や「廃棄証明書」を発行可能な業者を選ぶことで、万が一のトラブル時にも証拠を提示できます。
事前に契約書を交わし、秘密保持義務について明文化しておくと安心です。
電子データのメディア処分
書類同様、電子媒体に保存された個人情報も適切な消去・廃棄が求められます。
特に企業では、パソコンやUSBメモリ・ハードディスクなどの処分が甘ければ、重大な情報漏洩事故にもつながりかねません。
ポイントをしっかり抑えて、確実な処分を行いましょう。
メディアごとに異なるデータ抹消の必要性とリスク
メディアの種類によって、推奨されるデータの抹消方法が異なります。
ファイルをパソコンのゴミ箱に入れて削除するだけでは、専門ソフトさえあれば簡単に復元が可能です。
上書き消去や物理破壊、磁気破壊といった複数の方法を組み合わせることで、より安全性に処分することができます。
NIST SP800-88 rev.1に基づく安全なデータ抹消手順
アメリカ国立標準技術研究所(NIST)が発行するガイドライン「NIST SP800-88 rev.1」は、企業が遵守すべき安全なデータ消去についての国際基準として広く認知されています。
これに則って抹消手順を踏むことで、内部監査や外部監査にもしっかりと対応でき、安全に個人情報を管理できます。
データ抹消の証明と委託業者の選び方
データの抹消を外部の業者に依頼する場合は、作業の信頼性に加え、証明書発行の有無を確認することも大切です。
第三者機関の認証を受けている業者であれば、さらに安心して利用できるでしょう。
また、取り扱うデータの機密性に応じ、現地消去や立ち会い消去など処理方法を柔軟に選べる業者が理想的です。
まとめ
個人情報を含む書類や電子データは、不適切に処分することにより、情報漏洩など深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。
特に企業の場合は、法令遵守を前提とした処分ルールの策定と、信頼できる専門業者との連携が必要不可欠となるでしょう。
重要な書類を適切に取り扱い、完全な処分をお望みの方は、ぜひアズコムデータセキュリティへお任せください。
高いセキュリティ環境のもとで、確実な書類処分をさせていただきます。